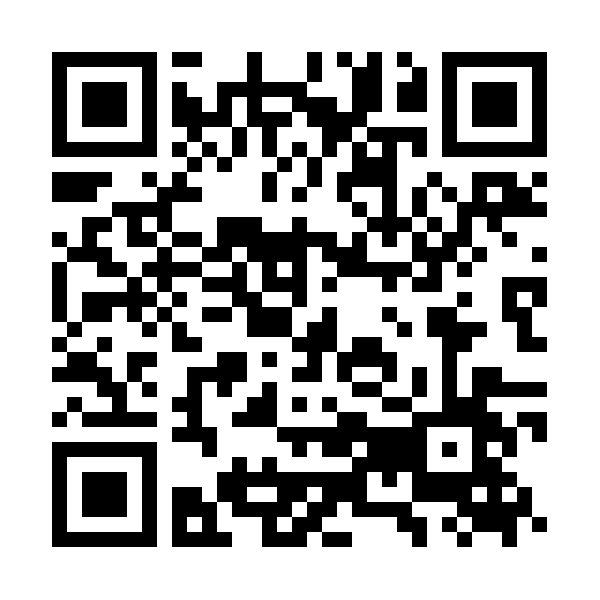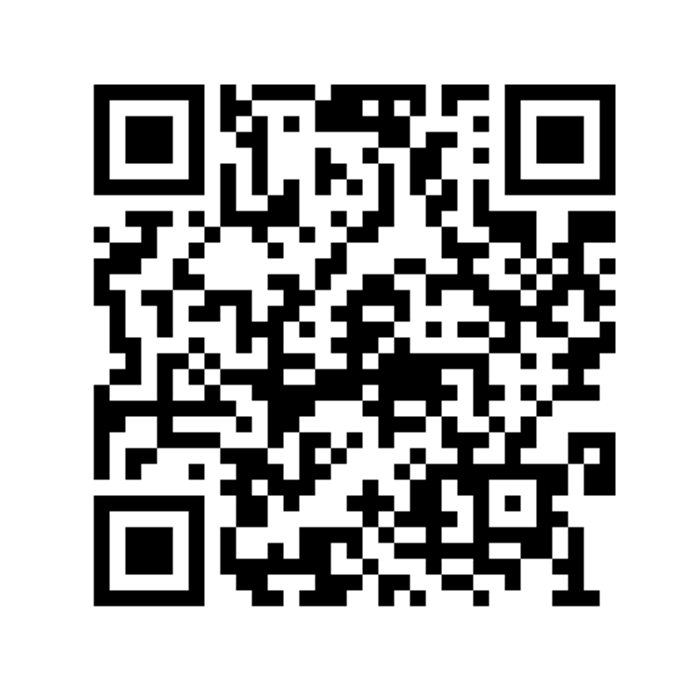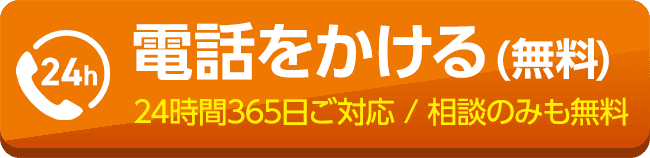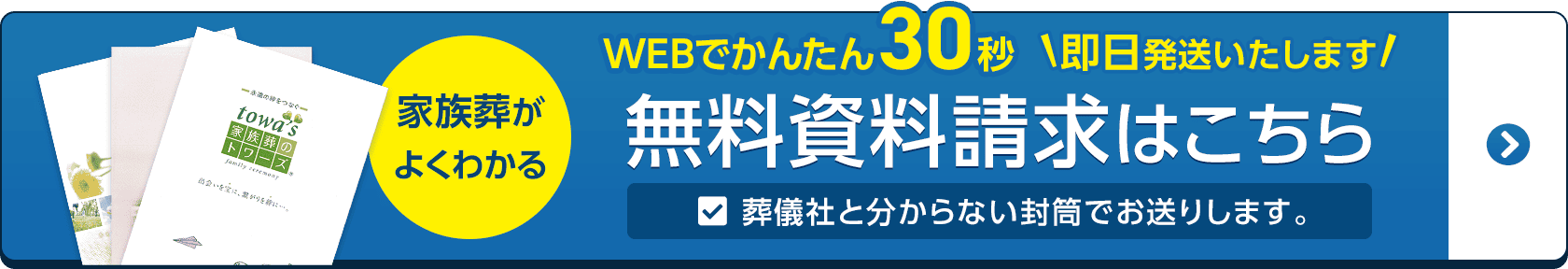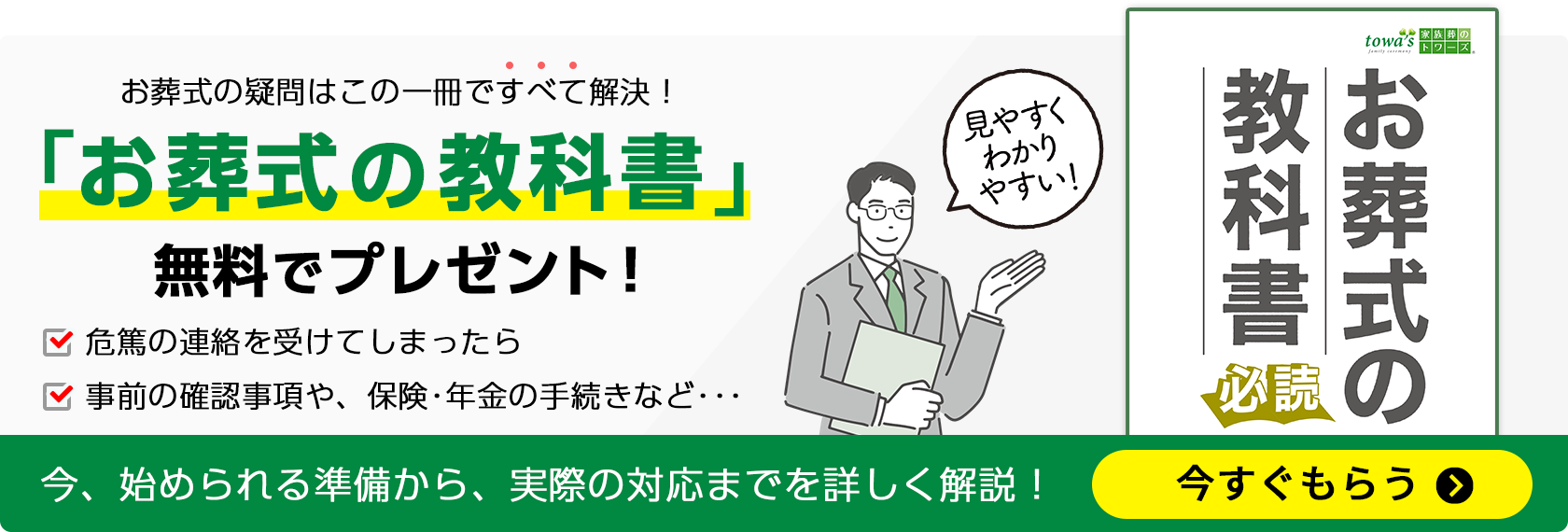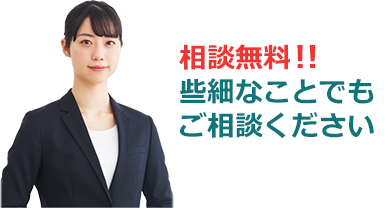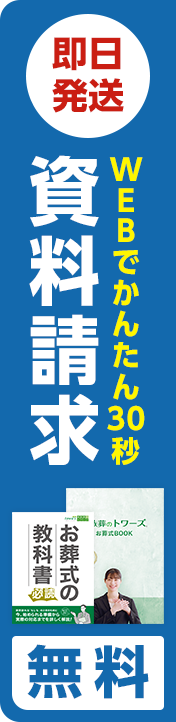пјңгҒҠйҰҷе…ёгҒЁгҒҜпјһ
гҒҠйҰҷе…ёгҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮж•…дәәж§ҳгҒ®гҒ”йңҠеүҚгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒз·ҡйҰҷгӮ„гҒҠиҠұгҖҒжҠ№йҰҷгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжҳ”гҒҜең°еҹҹгҒ®дәәгҖ…гҒҢеҠ©гҒ‘еҗҲгҒҶзӣ®зҡ„гҒ§гҖҒгҒҠзұігӮ„йЈҹгҒ№зү©гҒӘгҒ©гӮ’гҒҠдҫӣгҒҲгҒ—гҒҠйҰҷе…ёгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒҜ葬е„ҖгҒ®жҷӮгҒ«гҒҜиүІгҖ…гҒЁиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҒЁгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҫјгӮҒгҒҹгҖҒеј”ж…°йҮ‘гҒ®еҪ№зӣ®гӮ’гӮӮжһңгҒҹгҒҷйҮҚиҰҒгҒӘйўЁзҝ’гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒҠйҖҡеӨңгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜ葬е„ҖгҒ®йҡӣгҒ«жҢҒеҸӮгҒ—гҖҒгҒҠдҫӣгҒҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгғһгғҠгғјгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе®—ж•ҷгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҒ—гҒҚгҒҹгӮҠгӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гғһгғҠгғјгҒҢеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒзўәиӘҚгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҒҢеҗҲгӮҸгҒҡгҖҒгҒҠйҖҡеӨңгҒ«гӮӮ葬е„ҖгҒ«гӮӮеҸӮеҲ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҠйҰҷе…ёгӮ’йғөйҖҒгҒ—гҒҰгӮӮж§ӢгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгҒ®йҡӣгҒҜеҝ…гҒҡзҸҫйҮ‘жӣёз•ҷгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒдёҖиЁҖгҒҠжӮ”гӮ„гҒҝгҒ®иЁҖи‘үгӮ’ж·»гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
пјңгҖҖгҒҠйҰҷе…ёгҒҜиўұзҙ—пјҲгҒөгҒҸгҒ•пјүгҒ«еҢ…гӮ“гҒ§жҢҒеҸӮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖҖпјһ
гҒҠйҰҷе…ёгӮ’жҢҒеҸӮгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒҠйҖҡеӨңгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜ葬е„ҖгҒ®йҡӣгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠйҰҷе…ёгӮ’е·®гҒ—еҮәгҒҷгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒҠйҰҷе…ёиўӢгӮ’гғҗгғғгӮ°гӮ„гғқгӮұгғғгғҲгҒ®дёӯгҒӢгӮүгӮҖгҒҚеҮәгҒ—гҒ®гҒҫгҒҫе·®гҒ—еҮәгҒҷгҒ®гҒҜз„ЎдҪңжі•гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиўұзҙ—пјҲгҒөгҒҸгҒ•пјүгҒӢгҖҒгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°зҙәгӮ„зҙ«гҖҒгӮ°гғ¬гғјгҒӘгҒ©гҒ®ең°е‘ігҒӘиүІгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгӮөгӮӨгӮәгҒ®йўЁе‘Ӯж•·гҒ«еҢ…гӮ“гҒ§жҢҒеҸӮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжңҖиҝ‘гҒ§гҒҜеҸ°зҙҷгҒҢе…ҘгҒЈгҒҹж…¶еј”дёЎз”ЁгҒ®з•ҘејҸгҒөгҒҸгҒ•гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдёҖгҒӨз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁдҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮ
пјңгҖҖгҒҠйҰҷе…ёгӮ’е·®гҒ—еҮәгҒҷйҡӣгҒ®гғһгғҠгғјгҖҖпјһ
гҒҠйҰҷе…ёгҒҜгҖҒз·ҡйҰҷгӮ„гҒҠиҠұгҖҒжҠ№йҰҷгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ§ж•…дәәж§ҳгҒ®гҒ”йңҠеүҚгҒ«гҒҠдҫӣгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеҸ—д»ҳгҒ§гҒҠйҰҷе…ёгӮ’е·®гҒ—еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҸ—д»ҳгҒ§гҒ®гҒҠйҰҷе…ёгҒ®е·®гҒ—еҮәгҒ—ж–№гҒҜгҖҒгҖҢгҒ“гҒ®еәҰгҒҜиӘ гҒ«гҒ”ж„ҒеӮ·гҒ•гҒҫгҒ§гҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгҒҠжӮ”гӮ„гҒҝгҒ®иЁҖи‘үгӮ’иҝ°гҒ№гҒҹдёҠгҒ§гҖҒиўұзҙ—гҒӢгӮүгҒҠйҰҷе…ёгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҖҒдёҠжӣёгҒҚгҒ®еҗҚеүҚгӮ’зӣёжүӢеҒҙгҒ«еҗ‘гҒ‘дёЎжүӢгҒ§е·®гҒ—еҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
пјңгҖҖгҒҠйҰҷе…ёгҒ®зӣёе ҙгҖҖ пјһ
гҒҠйҰҷе…ёгҒ®йҮ‘йЎҚгҒ«жҳҺзўәгҒӘжұәгҒҫгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮж•…дәәж§ҳгҒЁгҒ®й–ўдҝӮжҖ§гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰжұәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж·ұгҒ„й–“жҹ„гҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒӘгӮӢзЁӢгҖҒй«ҳйЎҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘзӣёе ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдёЎиҰӘгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ5дёҮеҶҶгҒӢгӮү10дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҖҒиҰӘжҲҡгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°1дёҮеҶҶгҒӢгӮү5дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҖҒиҒ·е ҙй–ўдҝӮгӮ„еҸӢдәәзҹҘдәәгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°5еҚғеҶҶгҒӢгӮү1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҖҒйЎ”иҰӢзҹҘгӮҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°3еҚғеҶҶгҒӢгӮү1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒҢзӣёе ҙгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҖҒгҖҢ4гҖҚгӮ„гҖҢ9гҖҚгҖҒеҒ¶ж•°гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜйҒҝгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒҠйҰҷе…ёгҒҜж•…дәәж§ҳгҒёгҒ®гҒҠжӮ”гӮ„гҒҝгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’иҫјгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮй«ҳйЎҚгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжҖқгҒ„гӮӮгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒе…Ҳж–№гҒ®гҒҠйҰҷе…ёиҝ”гҒ—гҒ«й…Қж…®гҒҷгӮӢгҒ®гӮӮгғһгғҠгғјгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒҠйҰҷе…ёгҒ«з”ЁгҒ„гӮӢгҒҠйҮ‘гҒҜгҖҒгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒжә–еӮҷгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁе…Ҳж–№гҒ«жҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁеӨұзӨјгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜдҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҒҠжңӯгӮ’дҪҝгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гҖҒж–°жңӯгӮ’дҪҝгҒҶе ҙеҗҲгҒҜдёҖеәҰжҠҳгӮҠзӣ®гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒӢгӮүеҢ…гӮҖгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
пјңгҒ®гҒ—иўӢгҒ®йҒёгҒіж–№гҖҖпјһ
гҒ®гҒ—иўӢгҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ葬е„ҖгҒ§гҒҠйҰҷе…ёгӮ’еҢ…гӮҖйҡӣгҒ«гҒҜдёҚзҘқе„ҖиўӢпјҲйҰҷе…ёиўӢпјүгҒ«зҸҫйҮ‘гӮ’еҢ…гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮдёҚзҘқе„ҖиўӢгҒҜгҖҒгҖҢеҫЎйңҠеүҚгҖҚгӮ„гҖҢеҫЎйҰҷе…ёгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҹиўӢгҒ§гҖҒгӮігғігғ“гғӢгҒӘгҒ©гҒ§гӮӮжүӢи»ҪгҒ«иіје…ҘгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдёҚзҘқе„ҖиўӢгҒ®иЎЁжӣёгҒҚгҒҜе®—ж•ҷгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҸејҸгҒҜгҖҢеҫЎйҰҷе…ёгҖҚгҖҢеҫЎйҰҷж–ҷгҖҚгҖҒзҘһејҸгҒҜгҖҢеҫЎзҘһеүҚгҖҚгҖҢеҫЎзҺүдёІж–ҷгҖҚгҖҢеҫЎжҰҠж–ҷгҖҚгҖҒгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷејҸгҒҜгҖҢеҫЎиҠұж–ҷгҖҚгҖҢеҫЎгғҹгӮөж–ҷпјҲгӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҢеҫЎйңҠеүҚгҖҚгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжө„еңҹзңҹе®—гҒ§гҒҜж•…дәәж§ҳгҒ®йӯӮгҒҜгҒҷгҒҗгҒ«д»ҸгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҢеҫЎйңҠеүҚгҖҚгҒҜдҪҝз”ЁгҒӣгҒҡгҖҒгҖҢеҫЎйҰҷе…ёгҖҚгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҢеҫЎд»ҸеүҚгҖҚгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгӮігғ©гғ
дҫӣиҠұгҒ®зҹҘиӯҳ

пјңгҖҖдҫӣиҠұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®гғһгғҠгғјгҖҖпјһ иҰӘгҒ—гҒ„дәәгӮ„иҰӘж—ҸгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«иҙҲгӮӢиҠұгӮ’дҫӣиҠұгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиҙҲгӮӢеҒҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгғһгғҠгғјгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒдҫӣиҠұгҒҜйҖҡеӨңгҒҢгҒҜ…