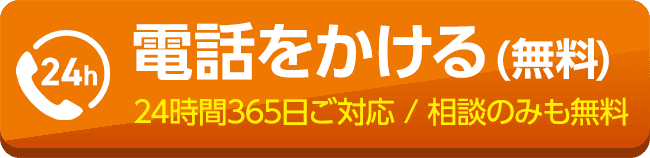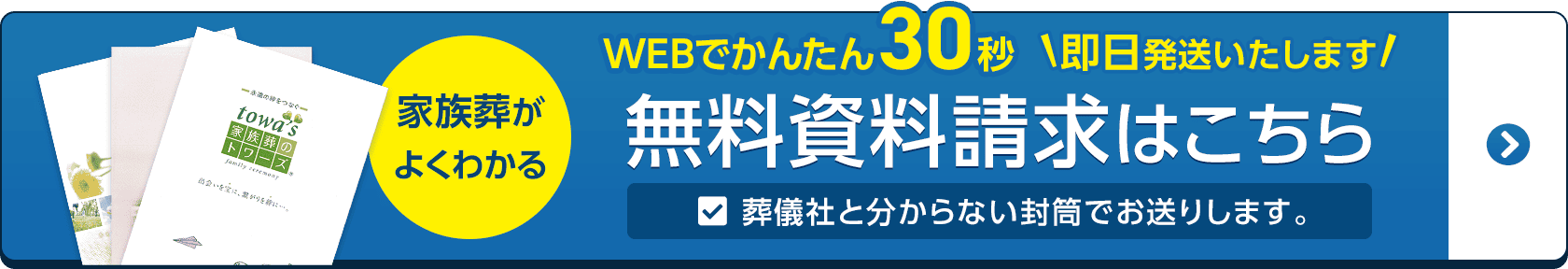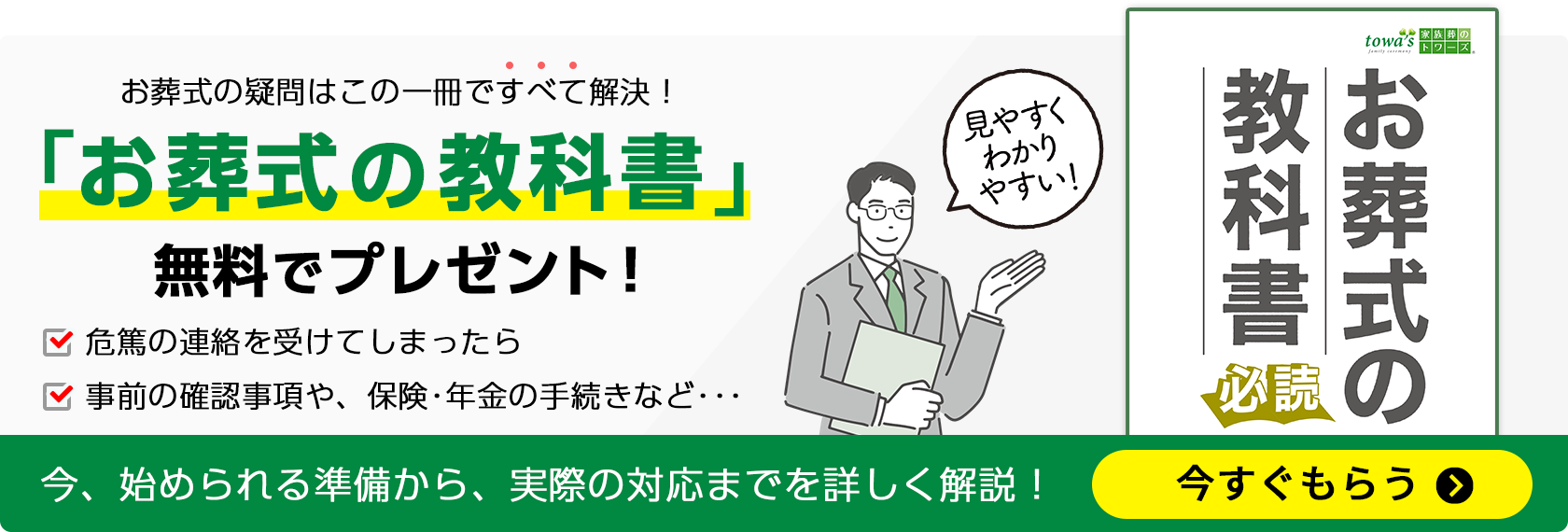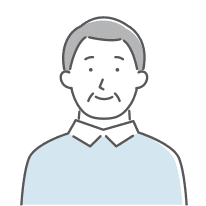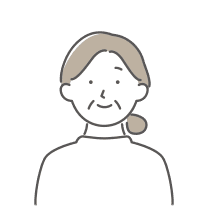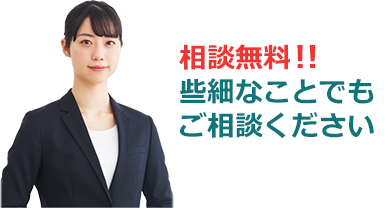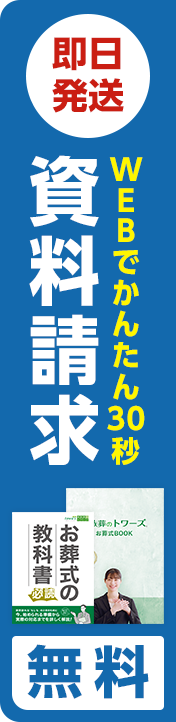жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒЁгҒҜ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҜгҖҒйҖҡеӨңгӮ„葬е„ҖгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҹйҡӣгҒ«иә«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢз©ўгӮҢгӮ’гҖҒиҮӘе®…гҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮз©ўгӮҢгӮ’жү•гҒ„гҖҒиә«гӮ’жё…гӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҜгҖҒеҸӨгҒҸгҒӢгӮүж—Ҙжң¬гҒ§дҝЎд»°гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹзҘһйҒ“гҒ®жҖқжғігҒ«ж №гҒ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҘһйҒ“гҒ§гҒҜгҖҒжӯ»гӮ„иЎҖгҒҜз©ўгӮҢгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢдәәгҖ…гҒ«жӮӘгҒ„еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒйҖҡеӨңгӮ„葬е„ҖгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒҹдәәгҒҜгҖҒж•…дәәгҒ«жӯ»гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹз©ўгӮҢгҒҹж°—гӮ’жҢҒгҒЎеё°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҜгҖҒгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁзҘһйҒ“ејҸгҒ®и‘¬е„ҖгҒ§гҒ®гҒҝз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜзҘһйҒ“гҒЁд»Ҹж•ҷгҒ®йўЁзҝ’гҒҢж··ж·ҶпјҲгҒ“гӮ“гҒ“гҒҶпјүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜд»Ҹж•ҷејҸгҒ®и‘¬е„ҖгҒ§гӮӮеҸӮеҲ—иҖ…гҒ«й…ҚгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӘгҒңгҒҠжё…гӮҒгҒ«еЎ©гӮ’дҪҝгҒҶгҒ®гҒӢ
гҒ§гҒҜгҖҒгҒӘгҒңгҖҢеЎ©гҖҚгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒҠжё…гӮҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгҒ®зӯ”гҒҲгҒҜгҖҒгҒҜгӮӢгҒӢжҳ”гҒӢгӮүдәәгҖ…гҒҢзөҢйЁ“зҡ„гҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеЎ©гҒ®жҢҒгҒӨеҠӣгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®зҘһи©ұгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”ҹжҙ»гҒЁгҒҠжё…гӮҒ
зҒ«и‘¬гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹжҷӮд»ЈгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒҜеңҹгҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…¬иЎҶиЎӣз”ҹгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҢгҒҫгҒ гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹй ғгҒ§гҒҷгҖӮ
еңҹ葬гҒ•гӮҢгҒҹйҒәдҪ“гҒҜи…җж•—гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҺҹеӣ гҒ§з–«з—…гҒҢеәғгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮдәәгҖ…гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҒҪгҒ„гӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒзөҢйЁ“зҡ„гҒ«еЎ©гҒ®жҢҒгҒӨеҠӣгҒ«зқҖзӣ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӨгҒ®дәәгҖ…гҒҜгҖҒзөҢйЁ“гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеЎ©гҒ«ж®әиҸҢдҪңз”ЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢеЎ©гҒ§зҒҪгҒ„гӮ’йҖҖгҒ‘гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҹҘжҒөгҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒ«дјқгӮҸгӮӢз©ўгӮҢгӮ„йӮӘж°—гӮ’зҘ“гҒҶжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ®иө·жәҗгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еЎ©гҒЁзҘһи©ұ
ж—Ҙжң¬гҒ®еҸӨгҒ„зҘһи©ұгҒ®дёӯгҒ«гӮӮгҖҒеЎ©гҒ«гӮҲгӮӢгҒҠжё…гӮҒгҒ®е ҙйқўгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҸӨдәӢиЁҳгҒ«гҒҜгҖҒгӮӨгӮ¶гғҠгғҹгғҺгғҹгӮігғҲгӮ’иҝҪгҒЈгҒҰй»„жіүгҒ®еӣҪгҒёиөҙгҒ„гҒҹгӮӨгӮ¶гғҠгӮ®гғҺгғҹгӮігғҲгҒҢгҖҒй»„жіүгҒ®еӣҪгҒӢгӮүзҸҫдё–гҒ«жҲ»гҒЈгҒҹеҫҢгҖҒжө·гҒ®ж°ҙгҒ§зҰҠпјҲгҒҝгҒқгҒҺпјүгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒз©ўгӮҢгҒҹиә«дҪ“гӮ’жё…гӮҒгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиЁҳиҝ°гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
зҘһйҒ“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеЎ©гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰиә«гӮ’жё…гӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҘһи©ұгҒҢиө·жәҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжө·ж°ҙгҒ®еЎ©еҲҶгҒ«гҒҜжө„еҢ–гҒ®еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ®еҪ№зӣ®
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ®еҪ№еүІгҒЁгҒҜгҖҒдёҖдҪ“дҪ•гҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮзҘһйҒ“гҒ§гҒҜгҖҒз©ўгӮҢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢж°—жһҜгӮҢпјҲгҒ‘гҒҢгӮҢпјүгҖҚгҒЁжӣёгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢж°—гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒдәәгҒҢз”ҹгҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж №жәҗзҡ„гҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠз”ҹе‘ҪеҠӣгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®ж°—гҒҢе®Ңе…ЁгҒ«жһҜжёҮгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§дәәгҒҜжӯ»гҒ«иҮігӮҠгҖҒиә«иҝ‘гҒӘдәәгҒ®жӯ»гҒҜгҖҒе‘ЁеӣІгҒ®дәәгҖ…гҒ«ж°—жһҜгӮҢгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢзҘһйҒ“гҒ®ж•ҷгҒҲгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒ«гҒҜгҖҒз”ҹе‘ҪгҒ®жәҗгҒ§гҒӮгӮӢжө·гҒӢгӮүдҪңгӮүгӮҢгҒҹзІ—еЎ©гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒз”ҹе‘ҪгҒ®жәҗгҒ§гҒӮгӮӢжө·гҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹеЎ©гҒҢгҖҒж°—жһҜгӮҢгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹдәәгҖ…гҒ«ж–°гҒҹгҒӘжҙ»еҠӣгӮ’дёҺгҒҲгҖҒдәәгҒ®жӯ»гҒЁгҒ„гҒҶйқһж—Ҙеёёзҡ„гҒӘзҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүгҖҒеҶҚгҒіж—ҘеёёгҒёгҒЁжҲ»гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҠ©гҒ‘гҒЁгҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ®жң¬еҪ“гҒ®еҪ№еүІгҒЁгҒҜгҖҒз”ҹе‘ҪеҠӣгӮ’еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгҖҒж—ҘеёёгӮ’еҸ–гӮҠжҲ»гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҖҒеҸӨгҒӢгӮүгҒ®жҷәж…§гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒ®дҪңжі•гҒЁгҒҜпјҹжӯЈгҒ—гҒ„иә«гҒ®жё…гӮҒж–№гҒЁжіЁж„ҸзӮ№
йҖҡеӨңгӮ„葬е„ҖгҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҸжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҠжё…гӮҒгҒ«гҒҜжӯЈгҒ—гҒ„жүӢй ҶгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гӮ’гҒ”еӯҳзҹҘгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶжҷӮгҒ«ж…ҢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ®дҪңжі•гҒЁгҖҒдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жӯЈгҒ—гҒ„гҒҠжё…гӮҒгҒ®жүӢй Ҷ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒ§гҒҠжё…гӮҒгӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«д»ҘдёӢгҒ®жүӢй ҶгҒ§иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҪ“гҒ«гҒӢгҒ‘гӮӢеЎ©гҒ®йҮҸгҒҜгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒҫгҒҝзЁӢеәҰгҒ§еҚҒеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮ
1. жүӢгӮ’жҙ—гҒҶ
гҖҖ-гҒҫгҒҡгҖҒжүӢгӮ’жҙ—гҒ„жё…гӮҒгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘжұҡгӮҢгӮ’иҗҪгҒЁгҒҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҝғиә«гӮ’иҗҪгҒЎзқҖгҒӢгҒӣгӮӢж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
2. гҒҠжё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’гҒІгҒЁгҒӨгҒҫгҒҝ
гҖҖ-з”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹжё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’гҖҒжҢҮе…ҲгҒ§гҒІгҒЁгҒӨгҒҫгҒҝеҸ–гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
3. иғёгҒ«еЎ©гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҸ
гҖҖ-еҸ–гҒЈгҒҹеЎ©гӮ’гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®иғёгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰи»ҪгҒҸжҢҜгӮҠгҒҫгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҝғиҮ“гҒ«иҝ‘гҒ„йғЁеҲҶгӮ’жё…гӮҒгӮӢж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
4. иғҢдёӯгҒ«еЎ©гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҸ
гҖҖ-ж¬ЎгҒ«гҖҒиғҢдёӯе…ЁдҪ“гҒ«еЎ©гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘеҲҶгҒ§иЎҢгҒҶгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҗҢдјҙиҖ…гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰгӮӮж§ӢгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиғҢеҫҢгҒӢгӮүгҒ®з©ўгӮҢгӮ’жү•гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
5. и¶іе…ғгҒ«еЎ©гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҸ
гҖҖ-жңҖеҫҢгҒ«гҖҒи¶іе…ғгҒ«еЎ©гӮ’жҢҜгӮҠгҒҫгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒи¶іе…ғгҒӢгӮүдҫөе…ҘгҒҷгӮӢз©ўгӮҢгӮ’жү•гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
6. еЎ©гӮ’жүӢгҒ§жү•гҒҶ
гҖҖ-дҪ“гҒ«жҢҜгӮҠгҒҫгҒ„гҒҹеЎ©гӮ’гҖҒжүӢгҒ§и»ҪгҒҸжү•гҒ„иҗҪгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
7. еЎ©гӮ’иёҸгӮ“гҒ§гҒҠжё…гӮҒзөӮдәҶ
гҖҖ-ең°йқўгҒ«иҗҪгҒЎгҒҹеЎ©гӮ’йқҷгҒӢгҒ«иёҸгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз©ўгӮҢгӮ’и¶іе…ғгҒӢгӮүж–ӯгҒЎеҲҮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гӮҲгҒҶ
еЎ©гҒ§гҒҠжё…гӮҒгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒдёӢгҒ®4зӮ№гҒ«ж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒ®еүҚгҒ«жүӢгӮ’жҙ—гҒҠгҒҶ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’жүӢгҒ«еҸ–гӮӢеүҚгҒ«жүӢгӮ’жҙ—гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒиә«гӮ’жё…гӮҒгӮӢдёҠгҒ§еӨ§еҲҮгҒӘиЎҢзӮәгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒйҖҡеӨңгӮ„葬е„ҖгҒ«еҸӮеҲ—гҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ”家ж—ҸгҒ«ж°ҙгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶзҝ’гӮҸгҒ—гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§ж…Јзҝ’гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгҒқгҒҶгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ”иҮӘиә«гҒ§жүӢгӮ’жҙ—гҒ„жё…гӮҒгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒ«йҒ•гҒ„гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒҜ家гҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҜгҖҒз©ўгӮҢгӮ’家гҒ®дёӯгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒзҺ„й–ўгҒ®дёӯгҒ§жё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’дҪҝгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ®жң¬жқҘгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’еӨұгҒҶиЎҢзӮәгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠжё…гӮҒгҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒ”иҮӘе®…гҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еЎ©гӮ’иёҸгӮҖгҒ®гӮ’еҝҳгӮҢгҒҡгҒ«
дҪ“гӮ’жё…гӮҒгҒҹеҫҢгҖҒжңҖеҫҢгҒ«жү•гҒ„иҗҪгҒЁгҒ—гҒҹеЎ©гӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁиёҸгҒҝгҒ—гӮҒгҒҰгҒӢгӮү家гҒ«е…ҘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒз©ўгӮҢгӮ’ж–ӯгҒЎеҲҮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
葬е„ҖгҒ®иҰҸжЁЎгӮ„дјҡе ҙгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҮәеҸЈгҒ«гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҢж’’гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒдјҡе ҙгӮ’еҮәгӮӢйҡӣгҒ«гҒқгҒ®еЎ©гӮ’иёҸгӮ“гҒ§гҒӢгӮүеё°е®…гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дҪҷгҒЈгҒҰгӮӮж–ҷзҗҶгҒ«гҒҜдҪҝгӮҸгҒӘгҒ„
гҖҢгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҖҒдҪҷгҒЈгҒҹжё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’ж–ҷзҗҶгҒ«дҪҝгҒҶгҒ®гҒҜзө¶еҜҫгҒ«йҒҝгҒ‘гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҜйЈҹз”ЁгҒЁгҒ—гҒҰиЈҪйҖ гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйЈҹеЎ©гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е®үе…Ёеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪҷгҒЈгҒҹжё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®гӮҙгғҹгҒЁгҒ—гҒҰеҮҰеҲҶгҒ—гҒҰж§ӢгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жё…гӮҒгҒ®еЎ©гҒҢжҢҒгҒӨж„Ҹе‘ігӮ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒҶжӯЈгҒ—гҒ„жүӢй ҶгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒж„ҸеӨ–гҒЁе°‘гҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒӮгҒҫгӮҠж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶж–№гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®ж©ҹдјҡгҒ«жё…гӮҒгҒ®еЎ©гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹйҒ©еҲҮгҒӘиә«гҒ®жё…гӮҒж–№гӮ’иә«гҒ«гҒӨгҒ‘гҒҰгҒҝгҒҰгҒҜгҒ„гҒӢгҒҢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒ„гҒ–гҒЁгҒ„гҒҶжҷӮгҒ«гӮӮгҖҒиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰеҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ„гҒ”дёҚжҳҺзӮ№гҒҢгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҒҠж°—и»ҪгҒ«е®¶ж—Ҹ葬гҒ®гғҲгғҜгғјгӮәгҒёгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
















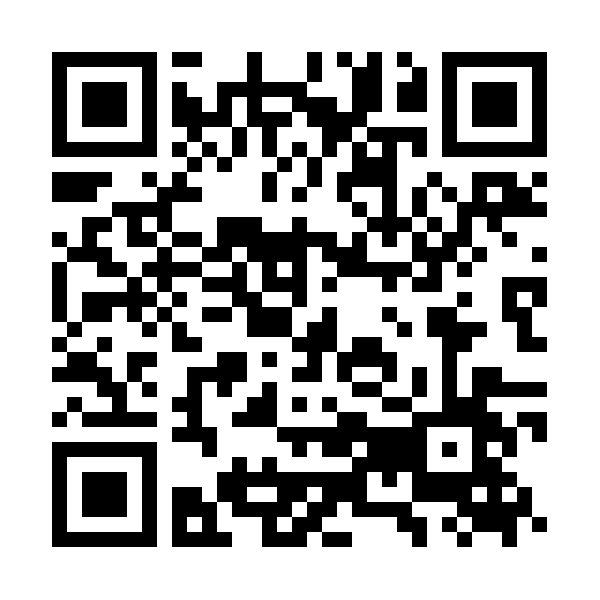
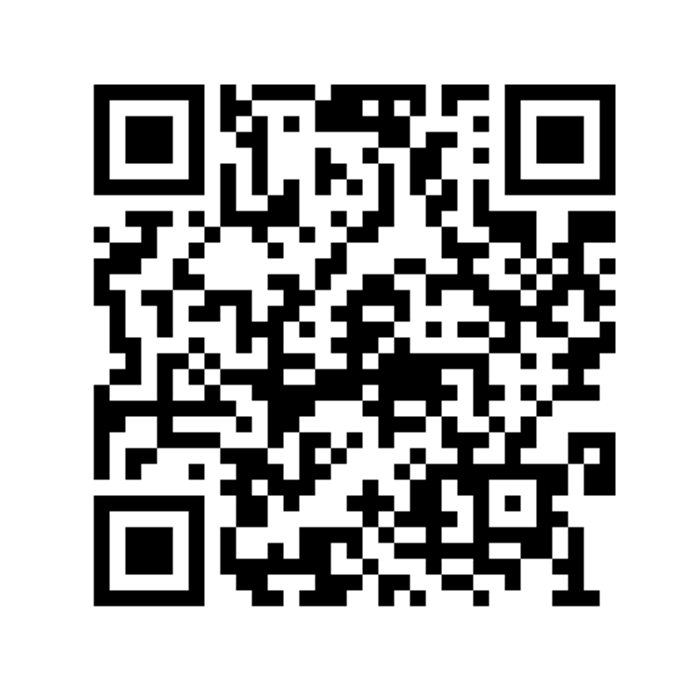
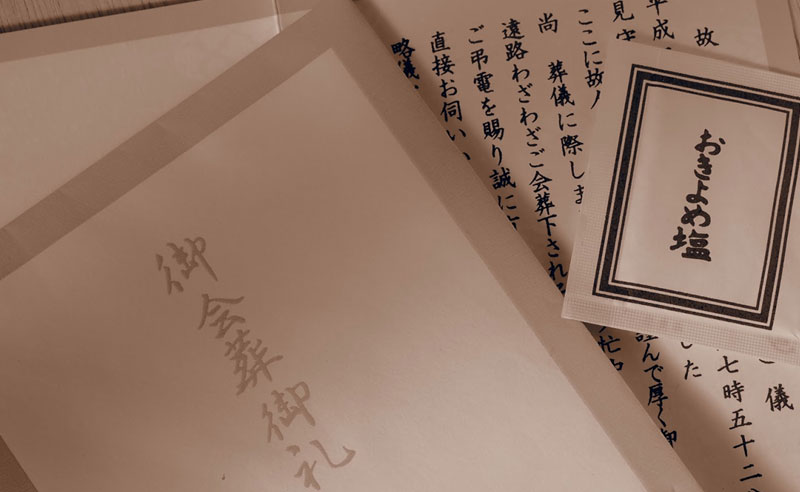









 葬е„ҖеҫҢ
葬е„ҖеҫҢ 葬е„ҖеүҚпјҲдәӢеүҚзӣёи«Үпјү
葬е„ҖеүҚпјҲдәӢеүҚзӣёи«Үпјү 葬е„Җгғ»гҒҠ葬ејҸ
葬е„Җгғ»гҒҠ葬ејҸ зөӮжҙ»
зөӮжҙ» еҸӮеҲ—гғһгғҠгғј
еҸӮеҲ—гғһгғҠгғј